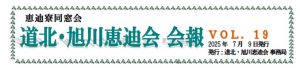アーカイブ
令和7年11月11日(火)第26回開識社講演会のご案内
[事務局からのお知らせ] [北海道支部] [北海道支部からのお知らせ]
かねてより北海道恵迪寮同窓会主催の開識社講演会活動にご関心をお寄せいただき篤く感謝申し上げます。
さて、今年の講演会のテーマはヒグマです。講師の先生はNPO法人もりねっと代表、ヒグマの会副会長、旭川市立大講師の山本牧氏です。福井県出身、北大入学と同時にヒグマ研究グループに入り。大学演習林ではヤブ漕ぎと地図読みを鍛えられ、2年生を3回繰り返してようやく学部へ。ここでも大らかな学風のおかげで、森とクマの日々を過ごす。北海道新聞社では主に環境、大災害、防衛などを担当され、道新退職後NPO法人などでヒグマと北海道の森林に深く関わっておられます。
人身被害や農作物荒らし、市街地侵入など、人間との軋轢が高まっているヒグマ。問題急増の背景には、個体数の増加とともに、人間社会の変容に伴うヒトとクマの距離感の喪失がある。解決には、クマ対策だけではなく、ヒト側の対応も欠かせない。過疎高齢化という日本社会の課題の一つとして、地域防災の視点からヒグマ問題を一緒に考えていただきます。
北海道に住む私たちにとってたいへん示唆あふれる貴重なお話しが期待できます。
日時:2025年11月11日(火) 17:30開場 18:00開演
会場:札幌時計台ホール(入場料無料)
(札幌市中央区北1条西2丁目)
講師:山 本 牧 氏 (昭和49年恵迪寮入寮)
演題:「ヒグマとどうつきあうか」
申込先:(担当) 内田 敏博
電話:090-9329-2484
※参加希望の方は、10月25日(土)までに電話又はメールにて連絡をお願い
します。
※一般の方々へも案内しており、多数の参加が想定されます。定数をオーバ
ーした場合は、お断りすることがあることを予めご了承ください。
以下をクリックしてポスター もご覧ください
ポスター
北海道恵迪寮同窓会 第17回恵迪夏祭り(ビール会)開催報告
[事務局からのお知らせ] [北海道支部] [北海道支部からのお知らせ] [支部のページ]
1 日 時 令和7年7月26日(土)12:00~14:00
2 会 場 浜焼き海鮮居酒屋「大庄水産 札幌・読売北海道ビル店」
3 参加者(敬称略) 高井(S31)、内藤(S40)、千川(S40)、八重樫(S41)、大谷(S43)、内田(S51)、清水(S52)
4 開催報告
高井先生の乾杯により宴が始まり、その後、一気に当時の話へと花が咲きました。
まず、「楡の木」「エルムの鐘」などが話題に上がりましたが、エルムの鐘は、いつまで寮にあったのか、決して爽やかじゃなく濁った音だったとか、横山理事長 (S31)も鳴らされていたというような貴重な証言がありました。また、ダイハツ(大阪発動機)オート三輪に纏わる話などなかなか普段聞けないような話で盛り上がりました。
最近の話としては、運転免許返納に伴って「運転できません」と記載された免許証となったことや交通違反したものの逆に警官に説教した話とか、政治の話など話題は尽きませんでした。
今回のお店の東京本社に偶然にも八重樫さんのお知り合いが勤めておられることがわかり、その方のご厚意から料理も奮発されており、美味しい料理でお腹を満たし、皆さん杯を重ねるごとに益々饒舌、和気藹々、元気一杯で楽しい時間を過ごしました。
明るい時間から飲む少しの罪悪感と優越感に浸りつつ、最後は、内藤会長の締めにてお開きとなりました。
報告(清水)
北海道大学総合博物館 見学イベント 開催報告
[事務局からのお知らせ] [北海道支部] [北海道支部からのお知らせ] [支部のページ]
北海道大学総合博物館 見学イベント 開催報告
北海道恵迪寮同窓会 常任幹事 佐野将義(H2)
北海道恵迪寮同窓会では、北海道開拓の村旧恵迪寮舎の環境整備と会員同士の親睦を目的として、毎年、草刈りを実施していますが、現在、旧寮舎の改修工事が行われており、旧寮舎周りの草刈りができない状態であるため、代わりの行事として6月28日(土)に北海道大学総合博物館を見学するイベントを開催しました。
参加者は8名。
北海道大学総合博物館の玄関前で集合写真を撮影後、博物館を見学しました。
当日は、夏季企画展示「人文的昆虫展覧会」のオープニングセレモニーが開催されており、多くの来館者で賑わっていました。
今回の見学では、特別に総合博物館の首藤光太郎助教に館内案内をしていただきました。
首藤助教は植物分類・系統学を専門としており、最近ニュースになっていた北大キャンパス内で毒性がある「バイカルハナウド」とみられる植物が見つかったとして調査にあたった先生です。
総合博物館の専任の先生から、裏話や逸話を交えながら展示物などの説明をしていただきました。たいへん貴重なお話を聞くことができ、有意義な見学となりました。
見学終了後に総合博物館の建物横で、参加者全員で明治45年寮歌「都ぞ弥生」を歌いました。
その後、中央ローンに移動してお弁当を食べながら交流しました。
今回は、例年開催しているイベントが開催できないことになり、急遽企画して開催したイベントでしたが、総合博物館からの協力を得られ、天候にも恵まれ、楽しいイベントになったと思います。
ご協力いただいた北海道大学総合博物館と館内案内していただいた首藤助教に対して、お礼を申し上げます。
第17回恵迪夏祭り(ビール会)のご案内
[事務局からのお知らせ] [北海道支部] [北海道支部からのお知らせ] [支部のページ]
北海道恵迪寮同窓会
第17回恵迪夏祭り(ビール会)のご案内
北海道恵迪寮同窓会の伝統行事である「恵迪夏祭り(ビール会)」の季節がやってきました。
これまで、サッポロビール「ライオン」や北大「カフェ de ごはん」」でやってきましたが、これらの会場では思うような開催ができないことがわかりました。
そこで、新規会場として昼からビールを自由に飲める会場ということで探してみました。皆様に堪能していただけるものと思っています。
真夏の札幌の午後をビールで楽しみませんか。
1 日時 令和7年7月26日(土)12:00~14:00
2 会場
・浜焼き海鮮居酒屋 大庄水産 札幌・読売北海道ビル店
・札幌市中央区北4条西4丁目1 読売北海道ビル2階
3 会費 4,500円 ≪料理7品・2時間飲み放題≫
4 申し込み
・7月22日(火)までに、入寮年・氏名を明記して、
下記の担当にメールで申し込んでください。
・担当:副幹事長 清水文彦
メールアドレス shimirin1106@gmail.com
第19回道北・旭川恵迪会寮歌祭報告
[事務局からのお知らせ] [北海道支部] [北海道支部からのお知らせ]
2025年7月5日(土)午後6時より、旭川トーヨーホテルにおいて第19回道北・旭川恵迪会寮歌祭が開催されました。今年も北大・小樽商大応援団対面式(7月6日 小樽開催)と重なってしまいましたが、恵迪寮同窓会から千川浩治副会長と大谷文昭常任幹事がご来賓としてご出席いただき、総勢12名での盛宴となりました。
寮歌祭は、請川尊史幹事(昭和51年)の司会のもと、ご来賓代表として千川副会長(昭和40年・応援団)からご挨拶をいただいた後、出席者の中で最年長の五味渕稔氏(昭和41年)による乾杯で始まりました。各参加者の会話と食事でしばし盛り上がった後、各参加者の発声により寮歌を皆で高唱しました。寮歌の演目・発声者は以下の通り。
1 蒼空高く翔?らむと(昭和2年)- 宜寿次盛生氏(昭和60年・応援団)
2 魔神の呪い(大正6年)- 伊東誠氏(昭和57年)-今回、初参加
3 津軽の滄海の(昭和13年)- 皆川吉郎幹事(昭和43年)
4 瓔珞みがく(大正9年桜星会歌)- 五味渕稔氏(昭和41年)
5 永遠の幸(札幌農学校校歌)- 村上昭男幹事(昭和43年)
6 タンネの氷柱(昭和8年)- 渡辺誠二幹事(昭和58年)
7 一帯ゆるき(明治40年)- 宮崎譲幹事(昭和48年)
8 花繚乱の(昭和32年)- 森満範幹事(昭和57年・応援団)
9 水産放浪歌- 大谷文昭氏(昭和43年・応援団)
10 春雨に濡る(大正12年)- 山本牧氏(昭和49年)
11 都ぞ弥生(明治45年)- 請川尊史幹事(昭和51年)
エール:森満範幹事(昭和57年・応援団)
それぞれの寮歌の合間に、千川氏や大谷氏から寮歌にまつわるエピソードをお話し頂き、諸説はあるものの参加者同士の考えを語り合う姿に学生だった頃の情景が蘇り、胸が熱くなった次第です。OBだけの議論なので答えが出るようなものではないのかもしれませんが、作者の想いを尊重しつつ、現役生が歌いやすいように変わっていっても良いのではないかとの意見に落ち着いたと思います。ご参考として、各寮歌で出された話題の一部は以下の通りです(あくまで参加者内での会話ですので、批判・異論はご容赦ください)。
○都ぞ弥生(明治45年)
・「花の香」とは桜のことか(桜はあまり香りがしないが・・)?
・「羊群声なく」牧舎に帰る、って本当?
○永遠の幸(札幌農学校校歌)
・アメリカ南北戦争時の北軍行進歌が元歌であり、歌うテンポも早いほうが良い。
(原曲が同じである同志社大学の応援歌「若草萌えて」はテンポが良い)
○春雨に濡る(大正12年)
・春雨に「ぬるる」であったが、現在は「ぬる」
・「王者の誇」の王者とは?
○タンネの氷柱(昭和8年)
・「無絃琴(つるなしごと)」とは?
○津軽の滄海の(昭和13年)
・「牧場添ひの野路」の「野路(のじ)」の読みが、現在は「みち」となっている
○時潮の波の(昭和21年)
・旅の朝早くは「明けぬ」か「明けね」か
○花繚乱の(昭和32年)
・「森に桂の火は燃えぬ」とは?
○水産放浪歌
・前口上にある「~一夜の快楽を~」の「快楽」は「かいらく」か「けらく」か
・蒙古放浪歌との違い
このように、寮歌と議論(会話)を織り交ぜながら会は進行したため時間が足りないぐらいでしたが、充実した宴となりました。
また、今回も宮崎幹事作の「都ぞ弥生」の1~5番の歌詞の情景を描いた絵画を持参いただき、宴に華を添えていただきました。
次回は、来年2026年7月4日(土)にトーヨーホテルで開催予定ですので、多くの方のご参加をお待ちしております。
PDFでもご覧ください 会報19
(文責:昭和57年入学・応援団 森 満範)